 |
 |
 |
 |
(�ʐ^��2013.10.23 �B�e)���H�e���a�ł������܂��Ă����������̌����������̂ŁA�ی�{�݂։^�т܂����B���̐l�̂������ł́u���̒��͓n��ł����A�����܂ꂽ�܂܈�N�قlj߂����Đ��サ���Ƃ���ł��B�����Ă��܂��B�쐶�ɖ߂�Ȃ��̂Ŏ{�݂Ɏ��e���܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł����B ���̒��͋��R�ɂ���ĕی삳��܂����B���ʁA�쐶�̐����͎��R�̒��Ŏ���ł��܂��܂��B���ꂪ������O�ł��B���͖쐶�̐������͐G��ʂ悤�ɂ��Ă���̂ł����A���̂܂܂ł͎Ԃɂ͂˂��Ă��܂��A���͔ɐB���ł͂Ȃ��̂Őe���̉\���͂Ȃ��ƍl���A�������Ă��܂��܂����B ���̎ʐ^���B���Ď{�݂��o�܂����B (�ʐ^������)�{�݂��o���肷��Ƃ��́A���������肵�A�K�����ʼnt�݂܂��B�ʐ^�͏��ʼnt�ł��B(�ʐ^�����E)24���ԂŒn�����������r���v (�ʐ^�E)�f�C�r�[�N���P�b�g�X�q�A���������r�b�g�E�K���A���C�O�}�A�J�i�_�̂��݂₰�A���Ŕ��̂͂�߂܂��傤�ˁB |
���{�ɂ�����J���j
�{���Ɋւ��钍�ӎ���
���̖ڌ���L�����L������̂���s���S�ȔN�\�ł��B�������}���قŖ{���߂���߂���m���߂܂������A�T���͂��ߕs�m�莖��������܂��B�����������Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B�L�ۂ݂ɂ͂��Ȃ��ł��������B�������邱�Ƃ��\�z���܂��̂ŃR�s�[���ւ��܂��B ���쌠�ɑ��鎄�̍l���́uHOME�E�J���ƌ��̌����_�v�����ɋL���Ă���܂��B�⑫�y�ю����͔N�\�̖��A�Q�l�����͂��̃y�[�W�����ɋL�q���܂��B
�u���̒m�V�v�̐��_
�N�\���쐬���悤�Ǝv���Ɏ��������R�������܂��B����(2013�j�̓J���̎��珑�������C���^�[�l�b�g�Ŋe�ƂŎ��炳��Ă���J���̗l�q���m�邱�Ƃ��ł��܂��B ����A�쐶�̃J���̗l�q����ʌ��J�����͋ɂ߂ċH�ł��B�l�̎�ŕߊl����₷���J���͗��l�҂̋]���ɂȂ莩�������̐��܂������y�n����A�ꋎ���Ă��܂��܂��B �����������������ƔN�z�҂͂����܂��B�������q�������͉ߋ��Ɣ�r���Ăǂ����R���ω��������̊����邱�Ƃ͂ł��܂���B���͉ߋ��̎����Ⴂ�l�����ɒm���Ă��炢�����̂ł��B �q���͂��납��l���J���j�ɊS�͎����Ȃ��Ǝv���܂����A �O���l�ƃJ���ɂ��Ă��b����@��ɁA���߂ē��{�̃J���j���炢�͌ւ�������Č���悤�ɂȂ肽�����̂ł��B������]�ނ̂Ȃ�ߋ����݂߂邱�Ƃ��d�v�ł��B �Ȋw�͐i�����܂����A���j�͂���Ԃ��܂��B �{���쐶�̃J�������{�l�Ƃǂ����j�����ł����������Ȃ����̂ł͂������܂����A���̒m�V�̐��_�ŔN�\���쐬���܂����B
| �Ñォ��ޗǎ��� | �Љ�� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �I���O1500 | ���R���q�E����M��(�A�j�~�Y���j | �i�����j�����嗤�ɂčb���������� | ||||
| �I���O500 | �߉�(565?�`478?) | �i�@���j�C���h�ɂĕ����N���� | ||||
| BC/AC | �@ | �i�@���j�T�b�肢 | ||||
| �I����538 | �����`�� | �i�@���E�v�z�j�{��R�}�E�� | ||||
| �i�@���j�����ˌÕ��@�L�g���Õ��Ɍ����_�`����� | ||||||
| �i�Α��j�@�T�� | ||||||
| �i�����j�T�ɂ��Ȃޓ`�� | ||||||
| 700�� | �s��(668�`749)�����Љ�� | |||||
| 715(��T1) | �����̐l��T���� | �����T������� | ||||
| 723(�{�V7)���N�_�T�Ɖ��� | �����̐l���T���� | �܂����┒���T������� | ||||
| 729(�_�T6.2) | �������̕� | |||||
| 729(�_�T6.8)�V���Ɖ��� | ���T���� | �V���M���m�S�N�̕������b���ɂ���T������� | ||||
| �������ォ�玺������ | �Љ�� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
| 1072(���v4) | ���Ɏ���ւ� | |||||
| 1125(�V��2) | �E���֎~�� | |||||
| 1130(�厡5) | ���Ɏ���ւ� | �i�����j�Y�����Y�`�������m�莖���A�����L�� | ||||
| 1140(�ۉ�5) | (�Y��)�u���b�Y��v��Җ��ځA������H�m���o�Q | |||||
| 1188(����4) | �E�����ւ� | |||||
| 1310 | �V�Í��a��,�����ƋT�����a�̂��r�� | �v�ؘa�̏� | ||||
| 1378(�V��4) | ���ǎґ嗬�s | |||||
| �]�ˎ��� | �Љ�� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
| �]�ˎ���͂��܂� | �u�E��������ʂɎ��炳��A�����肪����̔� | (�Δ�)�T��(����)���悭������ | ||||
| 1685 (�勝2) | ���ޗ���݂̗� | |||||
| 1701 (���\14) | �@ | �ԕ�Q�m��������ɐ��H���p | ||||
| 1709 (��i6) | �@ | ����j�g1646�`1709�v | ���ޗ���݂̗ߔp�~ | |||
| �]�˂ɂĉV��T�̕�����r�W�l�X�� �u�]�˕S�i�[�얜�N���v�Q�� | (�G��)�x�x�O�\�Z�i�}�u�B�c�̐��ԁv �����k��1760�`1849 | |||||
| �i�G��j�u�]�˕S�i�[���ݔN���v�̐�L�d1797�`1858�@ | ||||||
| (�G��)�u�T�얭�X�v�̐� ���F(1798�`1861) | ||||||
| 1803(���a3) | (�G��)�u���ʌ��T�}�v������� | |||||
| (�G��)�u�Q�T�Y��v�吼�֔N | ||||||
| (�G��)�u�T�}�v�~�R���� �u�T�v�u�K�v�͓�ō� | ||||||
| �������珺�a �����m�푈�܂� | �Љ�� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
| 1873(����6) | ���b�K������ | |||||
| 1892(����25) | ��K�� | |||||
| 1895(����28) | ��@ | |||||
| 1898(����31) | ���@�{�s(���ݑ��͐�L�����ߑ�195���Ɏ��瓮���̐�L���ɂ��ċL�q�݂� | |||||
| 1901(����34) | (����)�u�������Ƃ��߁v �Ό��a�O�Y�쎌�@�[���َ��Y��� | |||||
| 1905(����38) | (�����`���a��)�g�߂Ȑ����̏��̂����������� | �j�z���I�I�J�~�Ō�̈�C�� �����W�X�e���p�[�y�ї��l | ����F�킱�̍��J���� 40�`50�C����͂��߂� | |||
| 1911(�吳1) | ���p���ʖ����@�{�s | (����)�u�Y�����Y�v �Ό��a�O�Y�쎌�@�c���Ց���� | ����F��N�T�K���u���ԁv�K�Ŕ��� | |||
| 1918(�吳7) | ����������(��)�n�`�� | ��@���� | ����F��̉Ƒ��ɂ���āu���ԁv�u���e�v�u���Y�v�u�����Y�v�Ɩ��Â����� | |||
| 1922(�吳11) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 1928(���a3) | �����J�������n�V�R�L�O���w�� | |||||
| 1934(���a9) | ���{�쒹�̉�n�� | |||||
| 1939(���a14) | �u�̏W�Ǝ���v�n�����{�Ȋw����A�̏W�Ǝ���̉ | |||||
| 1941(���a16) | ����F��1867�`1941.12�v | |||||
| ���a��� | �Љ��/���� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
| 1950(���a25) | �������ی�@���� | |||||
| 1951(���a26) | �X�і@�{�s | |||||
| 1956(���a31) | �C�ݖ@�{�s | |||||
| 1957(���a32) | ���R�����@�{�s | |||||
| 1962(���a37) | ���{������ފw��ݗ� | |||||
| 1963(���a38) | ��@���������꒹�b�ی�@�ƂȂ� | |||||
| 1965(���a40) | ����؎�Z�}���n�R�K�����s | �͐�@�{�s | (���B)�u����b�K�����v �p��f�� | |||
| 1966(���a41) | �P�H�����ِݗ� | �u���{����ށv���`���[�h�E�R���X�����w�� | ||||
| ����؎�^�C�}�C�A�����E�L���E���}�K�����s | ||||||
| 1967(���a42) | �~�h���K�����y�b�g�V���b�v�ł悭��������悤�ɂȂ� | ��l�C�݃E�~�K���y�т��̎Y���n�V�R�L�O���w�� | ||||
| 1969(���a44) | �y�b�g�V���b�v�Ń��j�K��(50�p�H)�����̃T�C�g�̊Ǘ��Ҍ��� �e���j��������悤�ɂȂ� | |||||
| 1970(���a45) | �P�H�s�Ńy�b�g�̃A���C�O�}�����̃T�C�g�̊Ǘ��҂��ڌ� | ���{�쒹�̉���c�� | ||||
| 1971(���a46) | �����w�X���b�O��� �f�p�[�g�Ńw�r�W��y�b�g�W�J�� | �u�����v�ݒu�B�і쒡���璹�b�s���ڊ� | (����)�����T�[����� | �P�H�s�蕿�R������8�����~�h���K���̃T�~�[������n�܂� | ||
| 1972(���a47) | ���ꕜ�A | ���R���ۑS�@�{�s ���L�n�̊g��̐��i�Ɋւ���@���{�s | �@ | �@ | �@ | |
| ���G���}�Z�}���n�R�K���V�R�L�O���w�� | ||||||
| 1973(���a48) | �c��ڂɃJ�G����������O�̂悤�ɂ��� | ���c �v1891.8�`1973.12�v | ���R���ۑS�@�{�s | |||
| 1974(���a49) | �����̈���y�ъǗ��Ɋւ���@���{�s | |||||
| 1975(���a50) | ��������~�h���K�������� | �~�h���K���ɂ��T�����l�� ���ǎ����傫���� | (����)�����T�[����� | |||
| ���{�؎�̘b�V���[�Y�J���ƉY�����Y���s | �����E�L���E���}�K���V�R�L�O���w�� | |||||
| (����)��ł̂�����̂���쐶���A���̎�̍��ێ���Ɋւ�������͔���(���V���g�����) | ||||||
| 1976(���a51) | ���{�؎莩�R�ی�V���[�Y�A�����E�L���E���}�K�����s | |||||
| 1980(���a55) | (����)�����T�[����l�X�R�ɓ��{�����\�����ݔ��� | |||||
| (����)���V���g�������{���� | ||||||
| ��O��̃E�~�K���y�т��̎Y���n�V�R�L�O���w�� | ||||||
| 1984(���a59) | �b�l�̃G���}�L�g�J�Q�b�� | |||||
| 1985(���a60) | ���a40�N����_���� ���H�̃A�X�t�@���g�� | (�Q�[��)�u�X�[�p�[�}���I�u���U�[�X�v���� | ||||
| 1986(���a61) | ���a40�N���菬��̃R���N���[�g���J�� �A�X�t�@���g���ɂ���Ď��������� | (����)�u���ڂ�����܂���v ���т悵�̂蒘 �R���R���R�~�b�N�A�� | �u���߂̂��炵�v ���c�ߎ��������ˏ��[ �ʐ^������ | |||
| ���� | �Љ��/���� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
| 1990(����2)�n�����g�� | ���_�J�̌��� | ���{�E�~�K�����c��� | �~�h���K���nj�Q(�V���h���[��) �V���T���@�}�K�� | |||
| �J�G���̌��� | �u�̏W�Ǝ���v�x�� | |||||
| 1991(����3) | ���{�؎肤�����Ƃ��ߔ��s(���搯��x�O ) | �u���b�ی�@�v���� | (�A�j��)�~���[�^���g�^�[�g���Y �A�����J��i�E���{�ɂĕ��� | �u�Ăׂ���T -�T�A�S���w�ɏo��v �����z�g���M���[ | ||
| 1993(����5) | �@ | �@ | �u��̕ۑ��@�v���� | |||
| �@ | �@ | �u���꒹�ޖ@�v�u�쐶���A�����n�K���@�v�p�~ | ||||
| �@ | �@ | ��ł̂�����̂���쐶���A���̎�̕ۑ��Ɋւ���@���{�s | �u�J���������䂦�ɃJ������v�T�m�A�c�R�t�B�[���h���C | |||
| �@ | �@ | ����{�@�{�s �����̑��l���Ɋւ�����{�s | �u�C�V�K���̗� �킽���̃����_�[�݂����Ȑ������́v���v�ۍW�����X | |||
| 1994(����6) | �J�G���c�{�J�r�a���{�N�� | �ΐ쎁�����ɂăJ���R�Љ� | �u�����̃J��-�I�T���V�̐搶�J���ƕ�炷�v �ΐ�Ǖ㒘���⏑�[ | |||
| 1995(����7) | �J�G���c�{�J�r�a�� | �@ | (����)�u���߁I�v�Ȃ������킱 �T�ԃ��[�j���O�A�� | |||
| 1996(����8) | ���C���t���G���U���m����悤�ɂȂ� | �C�m���������̕ۑ��y�ъǗ��Ɋւ���@���{�s | �u�~�h���K���̎������v����璘�n�|�� | |||
| �u�����ށE��ނ̂ӂ����v�����O�Y���\�t�g�o���N�N���G�C�e�B�u | ||||||
| 1997(����9) | (�A�j��)�u�|�P�b�g�����X�^�[�v���� | �u�J���̂��ׂ�-�J���[�}�Ӂv���� �� �������o�� | ||||
| 1998(����10) | �C���^�[�l�b�g��ʂɕ��y | ���{�J�����R��������ݗ� | �u�J���̂Ђ݂v�F�c��t�q���|�v���� �u���߂��̂�����v�{�c�ەv�������o�� | |||
| 1999(����11) | �_�C�I�L�V���ޑ����ʑ[�u�@ | �u�~�h���K���A�[�j�K���̈�E�H�E�Z�v���� �G��(��)�� �K��(��) �ǂ��Ԃo�� | ||||
| �u����ȂɊȒP�I�~�h���K���E�[�j�K���̎������v跖�W�g(��) | ||||||
| �u�J�� �I�ѕ���ĕ��v���ėT�i�� ���W�ʐ^ �w���p�u���b�V���O���s | ||||||
| 2000(����12) | �J�~�c�L�K��������� | ���R�̃��j�K�����D�ƈ���J�~�c�L�K�����������o�� | (����)�u�����̃J�������v �X������ �T�ԏ��N�T���f�[�A�� | �u�J���f�B�J�J���̉ƒ��w �v���ƎR�m�� �A�[�g���B���b�W | ||
| �u�������݂�Ȃ�I�v��ΐ��꒘�W�p�� | ||||||
| �u�J�����v�����q�f�L�ʐ^ ���g�����A | ||||||
| �u�N���[�p�[�v�n���J������e����Y��Y | ||||||
| 2001(����13) | ���C�ȏ�]�Ǒ���(��) | ���C�ȏ�]�NJ����m�F(��) | ���R�u�a�i�ד����n�فu���E��ƂɐӔC�v����(��) | �u�T�̌Ñ�w�v��c���E�F�엲�v�� �����o�� | ||
| �u���߂���v�k��E�쒘���ԃf���A������ | ||||||
| 2002(����14�j | ���b�ی�@�̑���� | ����F��̃J���u���ԁv2001.7�v | �u�݂ǂ肪�߂䂤�䂤�̂т����肨����ہv �u�Γc�i���E����i �u�Γc�i�������� | |||
| �S�~�o�P�c�ŗA�����ꂽ�H��p�Y�̃N�T�K�������̃T�C�g�̊Ǘ��҂��ڌ����� | �u���b�̕ی�y�ю�̓K�����Ɋւ���@���v�ɖ��̕ύX | �N�T�K���u���e�v�u���Y�v�v �v�N���s���������m�F | �@ | |||
| 2003(����15) | �R�C�w���y�X���s(��) | ���{�Y�Ō�̃g�L�v | ���R�Đ����i�@�{�s | |||
| 2004(����16) | ��ΐ���A���C�O�}��Q�u�������̃T�C�g�̊Ǘ��҂��T�� | �a�T�ی�̉�ݗ� | ||||
| ���C���t���G���U�m�F���� | ���j�K�����Ԍ������@�l�ݗ� | |||||
| 2005(����17) | ���C���t���G���U����A�W�A���s | �����c�������@�l�J���l�b�g���[�N�W���p���ݗ� | �u�J���I�h�[���v�c���Ă܂� �����u�h�j�j�h�v�A�� | �P�H�蕿�R������9���~�h���K���̃T�~�[���v | �u�J��-��ĂĂ���ׂ���{�̐������̂�����6�v������W�p�� | |
| �����r���ǃE�T�M���� | ||||||
| 2007(����19) | ��1��A�W�A�E�����m���T�~�b�g�啪���J�� | �u�J���̗�����-�b���ɔ�߂�ꂽ2���N�̐����i���v ���R�����m�g�j�u�b�N�X | ||||
| �u�I�E�G���ƃ��[�C�v�C�U�x���E�n�g�R�t���� �m�g�j�o�� | ||||||
| 2008(����20) | �u�������l����{�@�v���� | �O�������A�J�E�~�K���ی� | ||||
| 2009(����21) | ������j�K���쐶�� | �O���J���쏜������ʂɒm���� | �I�����l�H�q���v��n�܂� | �u�J�����D��! ���ߋTKAME�}�Ӂv�݂̂��� | ||
| 2010(����22)���ې������l���N(���A) | �����u���s | �{�������ًT�y������ | �@ | �@ | �u�K���ȃ��N�K���̈�ĕ��v�c���z�ꏼ����������X | |
| 2011(����23) | �@ | �@ | �u�����K���v�C�V�������������V���� | |||
| 2012(����24) | ���̃T�C�g�̊Ǘ��҂̎��Ƃ��A���C�O�}��Q���� | ��� ����1949�`2012�v | �@ | �@ | �N�T�K���u�����Y�v�����H �������m�F | �u�T�̂Ђ݂v�c�����䒘 �v�`�u�d�o�� |
| �j�z���J���E�\��Ŏ�Ɏw��A�������l | �@ | �@ | �K���p�R�X���������T���W���[�W�v1910�H�`2012 | |||
| �ɓ��A���f�B�����h���� i Zoo�ĊJ�� | �@ | �@ | ||||
| 2013(����25) | �����|�X�g�J�����ꒆ�~�E�J��������T����ʂ��ăJ����������g�� | �u�J������m�[�g�v��J�ׁ@��Y��L���������V���� | ||||
| ���ȃ~�h���K���A���֎~������ | �u���̃J�����A���炤�v�������� | |||||
| 2014(����26) | ���ȃ~�h���K���A���֎~���j�ł߂� | |||||
| 2015(����27) | ���G���}�C�V�K���A�o�֎~���j | |||||
| 2016(����28) | �n�i�K�����ʊO�������w��10��1���{�s��NEW�I | |||||
| �Љ��/���� | �����E�o���� | �߁E�@�� | ���� | �J���̋L�^ | �o�ŕ� |
�N�\�⑫�y�ю���
�Ñォ��ߑ�ɂ���
�܂��ŏ��Ɂu�T�̌Ñ�w�v��c���@�F�엲�v(��)�����Љ�܂��B �������L�x�ł��B�N�\�ɂЂƂЂƂڂ������Ƃ���ł����A�����g�����̊m�F���ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�Ȃ��܂����B
�T�b�肢/�T�m�i���ڂ��j
���̔N�\������ɂ�����A�������Q�l����T���܂������A�u�T�b�肢�v�Ƃ������t���������炸���܂����B ��������̂͂��A���݂̌����҂́u�T�m�i���ڂ��j�v�ƕ\������Ă���悤�ł��B �u�T�m�\���j�̒n�w�ɔ�߂�ꂽ����Ȃ��̋Z���ق肨�����v ���A�W�A�~�يw����ڂ����̂ł��Љ�܂��B �܂��u�T�̌Ñ�w�v��c���@�F�엲�v(��)�Ŋ����`���ȑO�̐_�㕶���i���݂�����j���W���邱�Ƃ�m��܂����B
��40�N�O�̎��͗��j�Łu������������Ȃ��v�Ƌ����܂����B�C���[�W�͑��̒��ɃV���[�}���̏���������A�T�̍b�����ɂ��ׂĊ�����ŋg����肤�B ���オ�퐶����ɂȂ�Ɣږ�ĂƂ����V���[�}��������܂��B�N�\�͌��݂̌����ɏK���ċT�m�ƋL���邩�A�T�b�肢�Ƃ��邩�����܂����B
�̗��̋T��
�J���A���邢�̓J�G���Ɏ�����̐ł��B
�{��R�}
�Ñ�C���h�v�z�ŋT�̏�ɏۂ��̂��Ă��܂��B�����E�[��̓���ƍN�����T�̏�ɂ̂��Ă���f�U�C���ł��B���͂��̉ƍN�����������A�{��R�}��A�z���܂����B
�L�g���Õ��E�����ˌÕ������}
���N�Õ��Q���������k�Ɍ����}��z�u���Ă��܂��B�n���l�Ƌ��ɑ嗤���������{�ɂ���Ă�������m�邱�Ƃ��ł��܂��B ����ɂƂ��Ȃ��Č×����{�ɐ������Ă��Ȃ������ƒ{�������n�����Ă��܂����B
����
�Õ��ɕ`����Ă��錺���͋T�p�Ǝ֎p�̃y�A�ň�̓`���̏b�ł��B
�T�}(����)/�ۛ�(�Ђ���)
|
 |
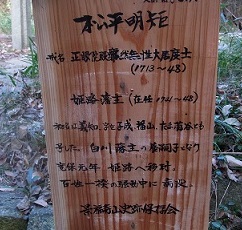 |
| (�ʐ^)�i�����̋T�}(2014.12.7�B�e) | (�ʐ^)�i�����R�j�Օۑ���̐��� |
�����Ƃ���ς����ƌ���̈���c��
 |
| (�ʐ^)�C�X�������C���h�l�V�A�̋�2013.6�B�e |
�n���l���嗤������`����Ƌ��ɋ������炳�ꋍ�������p����܂����B�������p�̍��Ղ͌�Ɏj����������܂��B�Ăш��܂��悤�ɂȂ�͖̂����ȍ~�ł��B �ޗǎ��ォ�畽������A�������l�C�ł��������͎E�����ւ��锭�߂��x�X�o�܂��B�����V�c�͎��D���ł����̂ŁA ���͎҂��u�������������疯�Ɋl��������肳�ꂽ�猙���v�Ƃ����v�f���Ȃ��ɂ����炸�ł���(�j���u���{��ًL�v)�A �]�ˎ���̐��ޗ���݂̗߂͓���j�g�̐M�S�����������ł��B����ł��l�Ԃ̓^���p�N�����K�v�ł��̂ŁA������H�ׂĂ��܂��܂��B ���{�l�͕�����_���̐M�S�ʼnߋ��E���������Ă��܂����B����ł͌���͂ǂ��ł��傤���B�u�E��������Ɣ���������v�Ƃ������݈ӎ�������悤�ł����A ����̓����̈���c�̂����Ă���܂��ƐM���q�ׂ�l�͂��܂���B�A�j���̉e���������Ǝ��͍l���܂��B�ނ�͒��ނ�M���ނƂ����������ڂ̂��킢�������̕ی�ɓw�߂Ă��܂��B ���R�ی�c�̂͂ǂ��炩�Ƃ����Ɨ��n���]�Ńo�N�e���A�������܂߂Ď��R�̃o�����X�𐮂��悤�Ɠw�߂Ă��܂��B ������Ƃ����Č�����{�l���܂������@���ς������Ă���킯�ł͂���܂���B���{�e�n�ɓ������{���E�肪��������A��������T�Ԃɓ����ԗ�Ղ��s���܂��B
�NjL�ł����A���̐e�ʂɑm��������܂��āA�����g���E�����b������Ɓu�ނ����v�Ƃ����܂��B ���̑m���͓�������c�̂Ƃ܂������W�Ȃ��l�ł����A���������킢�����Ă��܂��B���̑m���̎����Ă���e��13�˂ƕ����Ă���܂��B
�������̕ρE�����ɂ���
1988�N���������~�Ղ��瑽���̖؊Ȃ���������A���A�n�̎��瓮�����������Ƃ��킩��܂����B������������i�������Ă��܂����B����j�Ƃ��ĔN�\�ɏ��������܂����B
���b�Y��
�������ƃJ�G���̂������̊G�͒N���������m�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�Љ������A�z���Ɏx�z����E�����������Ă�������̒��ŕ`���ꂽ�G�����ł��B��҂͖��ڂł����A���H�m���o�Q(�Ƃ������傤�����䂤)�ł͂Ȃ����Ƃ����܂��B
���̓J���͕`����Ă��Ȃ��Ǝv������ł���܂������A�����H�|��w�����搶����u�J�����`����Ă��܂��B�v�Ƃ��w�E�����������܂����B�G�����͉Ђł��ɂȂ�܂������A���������݂��A�v�c�Ƌ����f�ȂɃJ�����`����Ă��܂��B
���̃J���͂��������Ƃ����Ă���̂������ŁA�������ꂽ�G�����̂Ȃ���ł̓T���ƃE�T�M�A�J�G�����͂��Ⴂ�ł���̂��J�����̉A����T�M�A�J�G���A�C�k���̓����ƈꏏ�Ɍ������Ă��܂��B
���m�Ȓ��H�G������̎n�܂�Ƃ���ƁA���̃J���͓��{�ŌÁA���邢�͐��E�ŌẪJ���̃L�����N�^�[�Ƃ����܂��傤�B
�ԕ�Q�m
�J���Ƃ͒��ڊW�Ȃ��ł����A�����ԕ�Q�m�̘b���Ă���܂��ƁA�����̍]�˂͐��H�����B���A�J�����Z�݂₷�����ł��������Ƃ������ł��܂��B�]�˒n�}�ŋT�Z�����T�ɂ��Ȃޒn�����悭���܂��B
�]�ˎ���̕����G�t�E��Ƃ���
��������̒��b�Y��̉e���������m�ȊG���o�Q(�����䂤�j�ɂ��Ȃ�Łu���H�G(�Ƃ�)�v�ƌĂт܂��B
�N�\�ɂ̓J�������`�[�t�ɂ����G��̖��̂��ڂ��܂����B
�Ⴆ�Ί����k�ւ́u�B�c�̐��ԏ����v�ł����A�J����A����������N���[�����ɂ���܂��B���N�̌����Ɣ��������J����k�ւ͕`���Ă��܂��B
�܂��A�N�\�ɍڂ��Ă��܂��A�]�ˎ���A�ז���̓��ӂȊG�`����������A����͎ʂ��A�}�ӂ����肠���Ă����܂����B
���Đl�������]������]�ˎ���̓��{�G��ɕ`���ꂽ�J�����ӏ܂��Ȃ���A�]�ˎ���̐l�X���J���ɂǂ��ڂ��A�ǂ̂悤�Ȋ���������Ă����̂��z������̂��y�������̂ł��B
�J���Ɋւ��钘��{�̋L��
�l�b�g�Ŕ̔�����Ă���{�i2013�N�j���Q�l�ɒ��o���܂����B ���͎����̒m��Ȃ������⎷�M�҂̑����ɋ����A�ǂ̖{��N�\�ɋL�ڂ��邩���������Ă��܂��܂����B���͖��ǂł��̂Ŋ��z�ׂ͂̂܂��A�q�����������l�����A���S�Ҍ����A�}�j�A�����l�X�ł��B �l�ɂ���Ė{�̚n�D�͈Ⴂ�܂��̂łł��邾������ɓn��A�����đ����̒��҂��L�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B����ł��ڂ�����܂���ł����B
�J���Ɋւ��钘��{�͎���{�������ł��B�쐶�̃J���̐��Ԃ�m��˂J���̎���̖{���͂킩��Ȃ��̂ł����A�쐶�̃J���ɂ��Ė{�ɂ��Ă��܂��Ɨ��l�ɍs���Ă��܂��l���o�Ă���̂Ŕ����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���܂����B ���l�҂͖쐶�̃J���̐��Ԃ�m�肽���l�ɂƂ��ĕ��Q�ł��B
�u�̏W�Ǝ���v���uCollecting and breeding�v�Ƃ����G��
����畽�����܂�̋T���D�ƂȂ�u���҂̃K�C�h�u�b�N�v�ł͂Ȃ����Ɗ��Ⴂ���ꂻ���ȃ^�C�g���ł��B
�Ƃ��낪�ǂ��������������҂��W�܂��Ċ�e�Ȃ���Ă����发�ł��B
�l�̖����H���═����y���Ă���������o�Ă��܂��B���̍��͎��瓮���͉ƒ{�ł���A�g�̉��̐����͌��߂�����Ă��܂����B
�������R���s���[�^�Q�[���Ƃ��͂Ȃ������̂ŁA
�q�������������̏W�ɖ����ɂȂ������������܂����B���j�̗���������L�ڂ��܂����B
(�ڍׁj���ҁ@���{�Ȋw����A�̏W�Ǝ���̉�A�̏W�Ǝ���ψ����
�x��1945�N3���`12���A1962�N8���`12��
1��1��(���a14�N1��)����52��12��(1990�N12��)�Ȍ�x��
�o�ŎЕϑJ�F�̏W�Ǝ���̉�(1��1���`38��3��)
�̕z�ҕϑJ�F���c�V�ߕސV��(1��1���`42��3��)
���L�F������1��1���`52��12���F�u�̏W�Ǝ��瑍�����v���{�Ȋw����̉�Ҋ�1991�N
�x������Ă����̂͑����m�푈�������灦�I��㍬���������A�����đ�w�����̍��ł��B
���I��㍬�����E�E�E�����ł͕ߗ������������Ԗ߂�A�s���s���҂̐���������t����ꂽ���A���邢�͓����ٔ����I��鏺�a23�N���܂łƉ��肵�܂��B
�@��
�@���ׂĂ��邤���Ɏ��̘Z�@�S���ɋL�ڂ���Ă��Ȃ��@��������̂ɋC�����܂����B�����Ő}���قœ����ɊW���邩�ȂƎv���@�����o���܂����B �W�Ȃ��@������������ł��邩���m��܂���B�����Ƃ�������l���ɓ���܂��ƃp�[�t�F�N�g�ł͂Ȃ��ł��B ���@�̓�����L���͉��N����͂��܂����̂��A���ɂ킩�炸�A���@�̐��肳�ꂽ�N�ɋL�q���܂����B�����̉\��������܂��B �Z�@�S���͒P�Ȃ铮���D���̎��ɂƂ��ēǂ݂Â炢�{�ł��B�������@���̐��Ƃ̐l�̒��ɂ������𗝉�����̂��炢�l�����������邩���m��܂���B ���͉ߋ��ɃC���J�ƃA�U���V�̈Ⴂ�𗝉��ł��Ȃ��l�ɈقȂ�_��������悤�Ƃ������Ƃ�����܂��B ���̐l�͖@�w�����̐l�ł����B�������Ă��l�����炩���Ă���̂������ł��Ȃ��̂Řb������̂���߂܂����B���̏��^�������Ɍ����Ȃ����o�Ɠ����Ȃ̂����m��܂���B
���b�ی�@
���b�ی�@�͚M���ނƒ��ނ��Ώۂł��B��ށE�����ނ͊܂܂�܂���B
�u���ԁv�u���e�v�u���Y�v�u�����Y�v�̔N��E�ڍׂ͕s��
����F��̒������}����ɂ���āu���ԁv�u���e�v�u���Y�v�u�����Y�v�Ɩ��t����ꂽ4�C�̃J���ɂ��āB���}����2000.6�v�̌��ǂ��悤��2001.7��C�́u���ԁv������ł��܂����Ƃ����܂��B�c���3�C�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̌�2�C�S���Ȃ��Ȃ� ���̋L���ł͍Ō�Ɏc�����̂́u�����Y�v�ł������Ǝv���܂��B�����Y�͒����f�W�^���̋L���Ŏ���҂ւ̎�ނŁu����12.12�ɓ~�������v�ƋL����Ă���܂��B���̍Ō�̈�C�̏����Y���S���Ȃ����H�a�̎R�̒n�����ɏ����Ă������悤�ȋL�����B���ł��B �܂�4�C�̔N������m�ɂ킩��Ȃ��B���݂́u�����Y�v������F�킪�����Ă������̂ł͂Ȃ��A�����̕��}����Ă����̂Ȃ̂��A�u���Y�v�Ɓu���e�v�̎e�Ȃ̂��A�܂������W�Ȃ��̂��ڍׂ͕s���ł��B�������̂��̂������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŔN�\�͕s���Ƃ��܂����B
����F��ɑ��鎄�̊��z
���͊w������A����F��́u�\��x�l�v��ǂ݂܂����B�����ǂ�ł��邾���ŁA�}�l�̎��͂܂Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�Ñォ��l�ԂƓ������[���������������Ă��邱�Ƃ͗����ł��܂����B�܂����낢��Șb�������Ƃ��Ď��W���邱�Ƃ͑�ł��B �J���̂��Ƃō�����(2013)����F��̖��O�ɐG���Ƃ͎v�������Ȃ������ł��B��Y�ł���c��Ȏ������܂Ƃ߂悤�Ǝc���ꂽ�l�������w�͂���Ă��܂��B
���j�K���E���j���y�b�g�V���b�v�Ō������̎v���o
���̗c�����̎v���o�ł��B����ȑO�ɂ���ނ̗A���͂��������Ƃł��傤�B�c�����̋L���ł����A50�p���炢�̃��j�K���̓K���X�����ɓ����ĊW������Ă��܂����B ���蕨�ł͂Ȃ����X�̌������Ƃ��Ē��������Ă����悤�ȋC�z�ł����B �e���j�͎q���������o���肵�₷�����X�ɂ����炢�ɓ�����Ĕ����Ă��܂����B
�G��Ɩ���
�䎌�̂Ȃ����̂��G��Ƃ��A�䎌�̂�����̂�ɕ��ނ��܂����B�Q�[����A�j���̒��ɂ��J�������`�[�t�ɂ����L��������l���̒��ԂƂ��ēo�ꂵ�܂��B (��)�X�[�p�[�}���I�u���U�[�X�E�|�P�b�g�����X�^�[�A �����̎q���������J���ɍD���������Ă��邱�Ƃ��f���m�邱�Ƃ��ł��܂��B �����A�j���A�Q�[���͌����ɂ��肦�Ȃ����z���E���y���ނ��̂ł����āA�u�����v�Ɓu��z�v�̔��ʂ̂��Ȃ��l�E���[���A�̒ʂ��Ȃ��l�ɂ͎��͂������߂��܂���B
�X�[�p�[�}���I�u���U�[�X
�J���͓G���ł����A�e���݂̂���L�����Ƃ��ĕ\������Ă��܂��B
�u���ڂ�����܂���v���т悵�̂蒘
���������̏��N��`�����q�������M���O����ł��B��l���̏��N�̓J���ƕ�炵�Ă��܂��B�Ёu�Ԏ��͌��v�̉���ɂ��A���ڂ�����܂���̍��@�̕~�n�̓J���̌`�����Ă���A�@��̂܂ɒr������T��������Ƃ������Ƃł��B�q�������̓J������D�����Ƃ������ƂŔN�\�ɂƂ肠���܂����B
�u�~���[�^���g�^�[�g���Y�v�@�A�����J��i
�q�������A�j���ł��B�A�����J�̃y�b�g�̃J�����E�҂̃~���[�^���g�ɂȂ舫�Ɠ����܂��B�q�[���[�̊��P�����E�A�����J���W���[�N�͂������ł����A ���͓����A�����J�l�́u�J���v�u�E�ҁv�̔��z�ɋ����܂����B�q�������̓J���̗v�f�����E�҂̗v�f�ɖ�����ꂽ�悤�ł��B ���{�j�═�m�����w��ł���l�̔E�҂̉��߂��猩�܂��ăA�����J�l�̔E�҂̕\���͈�a���������܂����A�A�����J�l���猩���J���E�E�ҁE���{�Ƃ��ĎQ�l�����ɂȂ�y���߂܂��B �䂪�Ƃɂ��܂��܃J�E�{�[�C�X�^�C���̃t�B�M���A���������܂��̂Ŏʐ^���ڂ��܂��B���p����������B�Ȃ�ƋT�̓����ł���b�������m���ʼnB��Ă��܂��Ă��܂��B ���ɂ��킦�Ă���̂̓^�o�R�ł͂Ȃ��L�����f�[�̂悤�ł��B���͂Ȃ����[�J�[�s���B
 |
 |
 |
| (�ʐ^)���� | (�ʐ^)���p | (�ʐ^)���p |
�u���߁I�v�@�Ȃ������킱��
��l�����ق̂ڂ̖���ł��B��l�̓J���ɖ��������߂܂��B���N�������f�B�A�ɓo�ꂷ��J���������J���̖{���𗣂�ߌ��ȍs�������鎖�ɔ�ב�l������i�ł��B
�|�P�b�g�����X�^�[
|
 |
 |
| (�ʐ^)���� | (�ʐ^)���p |
�u�����̃J�������v�X������
���N�����M���O����ł��B��l���̃J���������̐l�⓮����|�M���܂��B �O���̓J���̎��Ȓ��S�I�Ȗ{�\�����Ȃ�[�l�������Ă���A �㔼�̓J���Ƃ������F���l�̂悤�ɂӂ�܂��܂��B
���_�J�̌���
�쐶�̍����_�J���݂����Ȃ��Ȃ�܂����B�R���N���[�g�̏���ɂ̓��_�J�������Y�ޑ����͂��܂���B ���̐c��ڂ��Ƃ䂾���Ă��܂��̂œc��ڂł͗������݂܂���B�����₦������Ă���Ƃ���ɂ��܂��B ����20�N���냁�_�J�u�[�����N����܂������A���̎��͂����q���_�J��y�b�g�p�ɉ��ǂ��ꂽ���_�J�������l�����������悤�ł��B �J�_���V�����_�J�ƊԈ���č̏W���Ă���l���������܂����B |  (�ʐ^)�q���_�J |
������
�N�\�̒��ɃJ�G�����A�����A�����̕a�C���L�q���Ă��܂��B
�����r��͐�~�E�T�M��ʔ���
�z�[�����X�̎����Ă����E�T�M���ɐB�������́B�y��Ɍ����J���鎖�Ŗ�莋����܂����B�y�b�g�V���b�v�Ŕ����Ă���~�j�E�T�M�͐�������Ƒ傫���Ȃ�̂ĂĂ��܂��l�����܂��B���̍����̒m�l(�r��悠����̐l)�͉͐�~�ŃE�T�M���E���y�b�g�ɂ��܂����B�u�z�[�����X�������Ă����E�T�M�ł����H�v�Ɛq�˂�Ɓu�Ⴄ�v�Ɠ������܂����B�j���[�X�ŕ��Ă����ȊO�ɂ���ǃE�T�M�������Ƃ̂��Ƃł��B
�~�j�E�T�M�Ƃ������̂��̔����₷�����鑭�̂Ȃ�~�h���K���E�[�j�K�������̂ł��B���̂ł̔̔����y�b�g����̈���ƍl���N�\�ɉ����܂����B
�����T���E�W���[�W
���{�̏o�����ł͂Ȃ��ł����A���܂�ɂ�����ȃJ���ł��̂ŔN�\�ɂ̂��܂����B�K���p�R�X�����s���^���̃]�E�K���ł��B���N�������s���Ȃ��ߐ��m�ȔN��킩��Ȃ��ł��B�J���S�̂̉ۑ�ł����A�쐶�̂��̂�ی�E�ߊl���܂��̂ŁA�J���̐��N�����͕s���ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ��J���̎�����m��n�[�h���ɂȂ��Ă��܂��B
�A���C�O�}��Q/�ڌ�������n�������́E���b��Q��ۂɒʕ܂��傤�I�I
�A���C�O�}��Q�͕���16�N��ΐ���搶�̍u����Œm��A����24�N�Ɏ����̎��Ƃ���Q�ɂ����܂����B���̒��ɂ́u���킢���v�Ƃ����l������A�s���ɋ쏜�˗������Â炢�̂�����ł��B �������ł��̂Łu���̐l���˗������v�ƎE�����߈��̂悤�ɂ�����̂�����ď��ɓI�ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B�܂��A�s�������ł����ƍ����[���Ȕ�Q���Ă���l����������A ������D��ŋ쏜��㩂�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�A���C�O�}�̓L�c�l��^�k�L�ƈ���Ď�悪��p�ʼnƉ��╨���A�_�앨���������������Ă͕���o�����n����S���r�炵�܂��B �n���Ă��Ȃ��앨������������A�ނ������肵�܂��B�C�k�����ꂸ���\�ł��B�f�������Ō�ɂ��Ȃ��Ȃ����l�R�����܂��B���@���Ŏ��炵�Ă������_�J�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B������ �A���C�O�}������Ă���n��̐����������������Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��Ƃł��B�A���C�O�}����������Ă���l�q���ڌ�����Ă��܂��B��ꂽ�Ɖ��͒����܂���(����)�A����ꂽ���{�×������̋M�d�Ȗ��͖߂�܂���B �x����������������ΐ搶�ɒǓ��ƌh�ӂ̐S�Ő��v�N���L�ڂ��܂����B
���NjL(H14.9)�A�A���C�O�}���A�p�[�g�̂R�K�H�Ō��̂����������J�S���J���悤�Ƃ��Ă����b���m�F���悤�Ǝ��Ƃɓd�b�����܁A����Ɂu�}���V�����̂W�K�̃x�����_�ɂ��悶�̂ڂ��Ă����v�Ƃ����b�������܂����B ���w�Z��ɂāA�x�����_�ɕ���u���Ă�����A �c�Ȏq�������ĂĂ�������A���C�O�}�ڌ��̒ʕ�ɂ����͂�����������肪�����ł��B
�����ނ���ނ̌����E�ی�c��
�C���^�[�l�b�g�ŗ����ނ���ނ̌����E�ی�c�̂̑��݂�m��A�N�\�ɐ���ڂ������Ǝv���܂����B
�Q�l����
�u���{�j�N�\�E�n�}�v�@�g��O����
�u���{�̓`�L�@�����V�c�vP60�@�W�p�Ё@�w�K����@
�w�u���b�Y��v��ǂ݉���-�Y��̏d�w���A����сu�V�сv�ɂ���-�@�x�����݂�q
�wReading Chouju Giga:On Multiplicity of the Caricatures and "Play" �xImamura Mieko
�����H�|��w�|�p�w���I�v�@Vol.11(2005)�ʍ�
�u�Ԏ��͌��v��
�u�Z�@�S���v�L��t�@����25�N��
�u�T�̔�Ɛ����@�̈捑�Ƃ̐����咣�ƕ����̓��A�W�A�����̐��ρv�@�������N��
�u�T�m�\���j�̒n�w�ɔ�߂�ꂽ����Ȃ��̋Z���ق肨�����v ���A�W�A�~�يw��
�u�T�̌Ñ�w�v��c���@�F�엲�v(��)
�u�V�[�g���������T�vErnest Thompson Seton���@����g���Ė�@�I�ɍ������X ���A���C�O�}�̐���
�u�T��NET�v���C���^�[�l�b�g�������@�T�̎j��
(�y�[�W��)
Copyright (©) cyabane.mila All rights reserved.